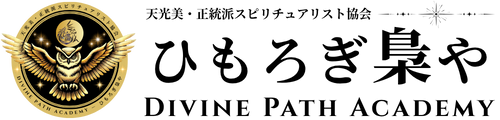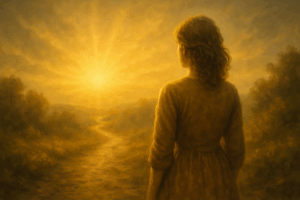スピリチュアルで生きたい。でも資格やスキルが増えるほど『まだ足りない』と感じてしまう理由
こんにちは。天光美・正統派スピリチュアリスト協会「ひもろぎ梟や」の上山純慶です。
今回は、スピリチュアルで生きたい、でも「資格やスキルを積めば積むほど、なぜか『まだ不十分かもしれない』という気持ちが強まる…」そんな気持ちに悩むあなたの心に、そっと寄り添う話をお届けします。
努力を重ねて、たくさん学び、資格を手にしているにも関わらず、胸の奥の“満たされなさ”が消えない──その苦しさには、あなたの真っすぐな姿勢と責任感、そして心の繊細さが関係しているのかもしれません。
実は、この「スキルが増えるほど不安が大きくなる」という心理には、立ち止まって静かに見つめる価値があります。というのも、心理学の世界には“心のズレ”が不安を生むという理論があるのです。
その第一歩として、以下のテーマで探ってみましょう。
- 私たちの「理想の自分」と「現実の自分」とのズレが、不安の火種になるしくみ
- 完璧を目指すあまり、心に負担をかける“多層的な完璧主義”の罠
- そして、日常でつい自分を追い込んでしまうクセの存在と、その優しい手放し方
「なぜ安心できないのか」という問い自体が、あなたが本当に大切にしている“在り方”を映し出しています。そして、それに気づくことが、安心の土台を築く一歩になるのです。
今回の記事ではまず、“理想と現実のズレ”がなぜ心に不安をもたらすのかを、心理学的にわかりやすく解きほぐしていきます。一緒に、安心への小さな光を見つけていきましょう。
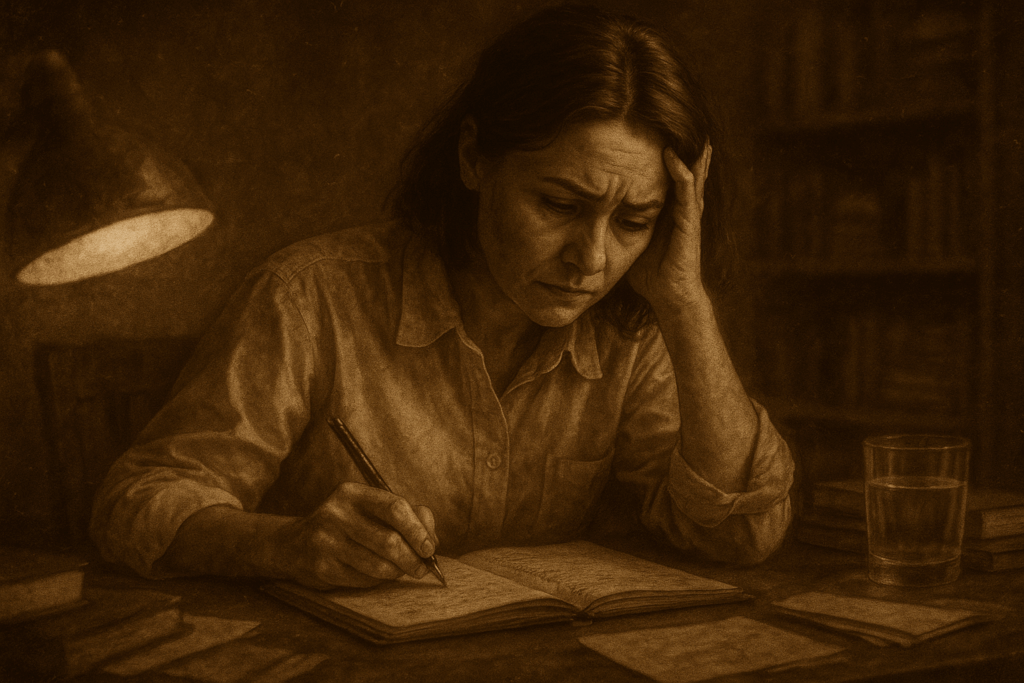
頼りになるのに揺れる心
いつもスキルアップに真摯に向き合っているあなたへ、優しい言葉を贈ります。
資格を取得したり、知識や技術を磨く努力を重ねることで、通常は自信が育つものです。
ところがなぜか
「もっと足りないのでは…」
「本当は自分が足りていないのでは」
といった揺らぎが、心の奥でじわり広がってしまうこと、ありませんか?
それは、あなたが自分に対してただ努力しているだけではなく、
「より良くありたい」
「人を導ける存在になりたい」
という思いを強く抱えているからかもしれません。その思いが本物の情熱であるほど、良い現実を望む心とのズレが気になることもあります。
完璧主義の罠
努力家のあなただからこそ、資格やスキルを積み重ねても「まだ足りない」と感じてしまう。
その葛藤の奥には、“多面的な完璧主義”という心の構造が関係しているかもしれません。
心理学では、完璧主義を一面的に捉えるのではなく、「多次元的(マルチディメンショナル)完璧主義」として分類する視点があります。例えば、自己に対する要求だけでなく、他者からの期待や社会からの評価を強く意識する“多層的な完璧主義”モデルです。
引用:(en.wikipedia.org) ウィキペディア
この多次元性には主に以下のような構成があります。
- 自己志向的完璧主義:自分自身に「もっと高く、もっと深く」と求めるタイプ。
- 他者志向的完璧主義:他人にも自分と同じレベルの完璧さを期待してしまうタイプ。
- 社会的規定型完璧主義:周囲が自分に完璧を求めていると感じ、その期待に応えようとしてしまうタイプ。
引用:kakakakakku blog内向型人間の進化論 | Introverted human Evolution
これらが複合して働くことで、「自分はまだ道半ば」という不安が深まります。スキルや資格が増えても、なぜか自信という形には結びつきにくく、むしろ「もっと」「もっと」と心が追い立てられてしまうのです。
このような完璧主義の罠に気づき、「なぜそう感じてしまうのか?」と自分の心の構造を理解することが、まずは安心への第一歩になります。
次のステップでは、そんな心の声を受け止めながら、自らを穏やかに労わるヒントも考えてみましょう。
自己肯定感をそっと守るためにできること
資格を積み重ねながら、つい「まだアレができていない」「もっと深く学ばなくちゃ」と自分を追い詰めてしまう――そんな“日常の声”にドキッとすることはありませんか?
その声は、あなたが大切な使命や理想と真剣に向き合っている証でもあります。でも、毎日の中でずっと続くその声は、知らず知らずのうちに心に重荷となって響いてしまうこともあります。
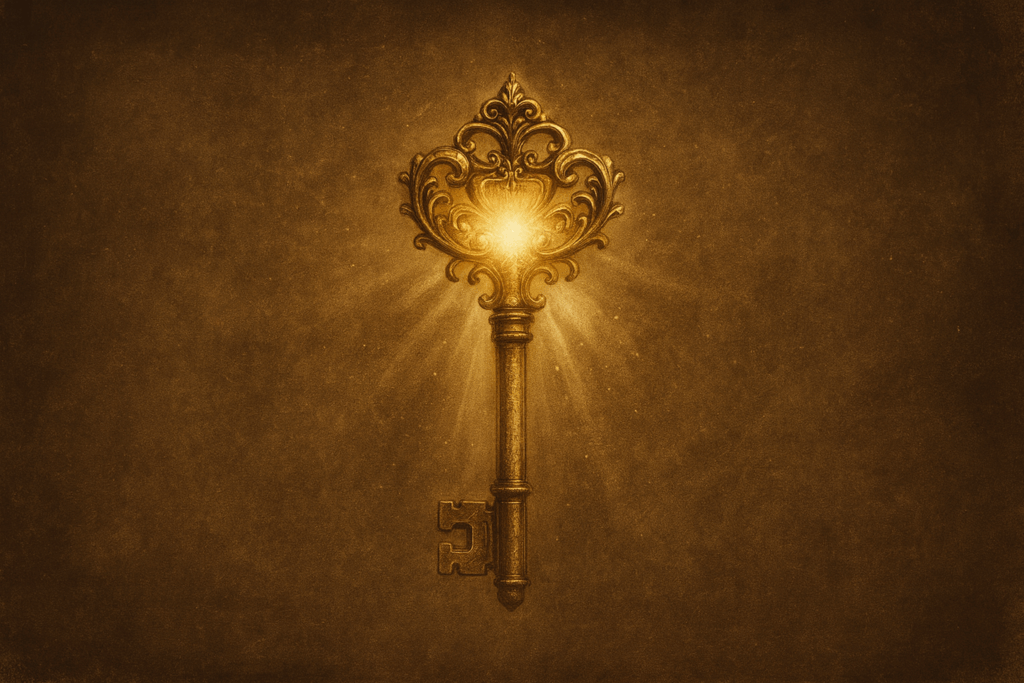
心理学では、このような自己批判的な内なる声を「インナークリティック(内なる批判者)」と呼び、人間が自らを評価し、時には責める心の構造として捉えられています。この声は、過去の経験——とくに幼い頃に「十分じゃない」「もっと頑張らないと」と繰り返された声の記憶——が背景になって形成されることもあります。大人になっても、その声が「まだ足りない」と心の中で繰り返されるのです。Psychology Todayウィキペディア
さらに、内なる声が習慣化した結果として「自分には常に努力が足りない」という思いが繰り返されると、それが「当たり前」の基準になり、自己肯定感は少しずつ薄れていきます。こうした自己批判の繰り返しは、不安や疲労を常に育て、心に静かな重りをかけてしまうのです。Psychology Todayウィキペディア
まずは、その日常の声に「どんな声が聞こえているかな?」と優しく耳を澄ませてみませんか?
「ほんとうは、できたこともあるよね」
「今の私にも価値ある」
という小さな言葉を、心にそっと置いてみるだけで、自分への眼差しがやわらかくなります。
その声は、あなたが今も一歩ずつ前に進んでいることへの祝福のはず。そんな心に寄り添いながら、“安心へつながる小さな実践”を、また一緒に考えてみましょう。
まとめ
ここまで、自分を責め続けるメカニズムを見てきましたが、そこから抜け出すカギは「自己信頼」にあります。いきなり大きな変化を求めなくても、日々の小さな行動や感覚に目を向けることで、心は少しずつ変わっていきます。
たとえば、今日できたことを振り返り、自分を褒める習慣を持つ、失敗しても「それも成長の一部」と優しく受け止める――そんな日々の積み重ねこそが、“在り方”の変化への一歩になります。
技術よりまず、自分を許せる在り方から始めませんか?その在り方こそが、安心の土台になり、スキルを安心に変える魔法になります。
技術よりまず、自分を許せる在り方から始めませんか?その在り方こそが、安心の土台になり、スキルを安心に変える魔法になります。